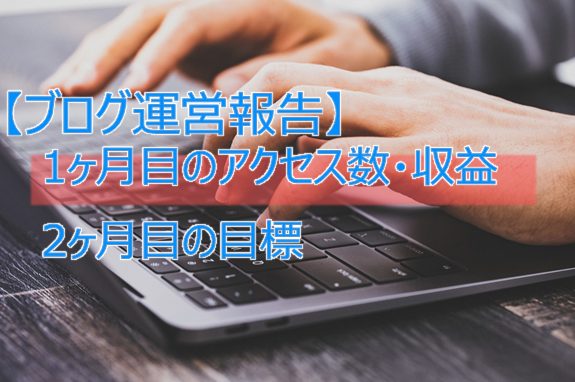こんにちは、週活SEです。
今日はディスプレイに関するsRGB/Adobe RGB/DCI-P3について調べてみました。
なおディスプレイ購入時にはHDR/DisplayHDRなどの機能も重要になってきますので、合わせてこちらの記事も参考にしてみてください。
sRGB/Adobe RGB/DCI-P3/Display P3
それぞれの規格のカバー率が高いほど、多くの色を表現できるといえます。
私はディスプレイ購入時に色々な色域の規格が出てきて困っていましたが、4種類程度が主流ではないかと思われます。
- sRGB はIEC(International Electrotechnical Commission)が提唱した国際規格。
- Adobe RGBはAdobeが提唱したRGB空間定義。
- DCI-P3はDCI(Digital Cinema Initiatives)が提唱したデジタルシネマ規格。
- Display P3はDCI-P3はAppleが提唱したDCI-P3の色域をベースとした新しい色域規格。
sRGB
sRGBはWindows環境における標準の色域。
撮影や印刷など特にこだわりがない場合は、普及しているsRGBに統一することで撮影機材や印刷、ディスプレイ表示などの入出力時の差を小さくすることが可能です。
ディスプレイでは、一定の価格を上回るとほとんどの製品がsRGBカバー率99%となっているが、後述する比とカバー率の違いには注意したい。
デザイナー向けのsRGB カバー率100%で、かつ4kモニターだとこちら。
色に関する口コミ評価としてはかなり高いと思います。
sRGB カバー率100%で、4kではなくWQHDであれば、比較的リーズナブルなディスプレイも多いです。品質で評価の高いBenQさんのディスプレイがおすすめです。
Adobe RGB
Adobe RGB は sRGB に比べ、より広い範囲の色域を持ち、sRGB に比べると特に緑色の領域が広い。
簡単にいうと Adobe RGB のカバー率が100%であれば、 sRGB の色域をすべてカバーしているといえますが、Adobe RGB を100%カバーしているディスプレイは少ないです。
そのため sRGB カバー率を99%以上、Adobe RGB カバー率が高い方がいいという場合は、Adobe RGB カバー率だけで選択してしまうと、sRGB カバー率が低い製品があるかもしれませんので注意が必要です。
ちなみにAdboe RGB カバー率100%の製品で、4kモニターになるとかなりお値段が張りますが、一度使ってみたいですね。
Adobe RGB カバー率99%、WQHDだとこちら。4kに比べると解像度は低いものの十分綺麗です。
DCI-P3
デジタルシネマ規格とあるように、映像撮影に使われるカラーフィルムの色域に対応した、比較的広範囲の色域を表現できる規格。
映像向けの規格のためか、Adobe RGB 規格と比べれると対応を謳っている製品は少ない気がします。
こちらもBenQさんから発売されているディスプレイ。口コミ評価はかなり高いです。
4kかつDisplayHDR600にも対応しているフィリップス製のディスプレイ。口コミ評価は要確認ですね。
Display P3
DCI-P3規格をベースにAppleが汎用性の高いデジタルコンテンツ向けに策定したもの。
Display P3 のカバー率が高ければ、同時にDCI-P3カバー率も高いということがいえます。
比とカバー率の違い
比率ではなくカバー率で機器を選択
Adobe RGB比◯%といった比率は面積比であり、Adobe RGB色域を全てカバーしている製品というわけではありません。
簡単にいうとAdobe RGB比120%の場合、Adobe RGBがカバーしている色域面積に対して120%というだけであり、Adobe RGB色域をすべて網羅しているわけではありません。
逆にAdobe RGBカバー率◯%と記載があれば、どこまでAdobe RGBを色ズレがなく再現できるのかが明確であり、入出力機器で規格の選択しやすいということがいえます。
よって機器を選択する場合は、比率ではなく、カバー率で機器を選択するほうが良いということがいえます。
sRGB/Adobe RGB 色域変換
色域変換機能がないと、用途に応じて最適な色を表現することができない。
色変換機能がなければ、どちらか片一方の方の規格で色域表現することが必要となるため、Adobe RGBに対応していてもsRGB色域設定にすると、Adobe RGB 色域が本来の表現にならず、sRGB 色域に変換されてしまい本来の色域が表現できない。
よって、 sRGB/Adobe RGB など、色域変換機能があることが好ましいと言える。